地震発生後の避難行動について
まずは落ち着いて身の安全確保が第一です。
東日本大震災は、これまでの予想を遥かに超える大津波により、尊い多くの命が奪われ、未曾有の被害がもたらされました。
このような状況の中で、市としても市民皆様の生命と財産を守るため、より安心で安全な生活環境を推進するため、地域防災計画をはじめとする諸計画の見直し作業に着手したところでありますが、これらの諸計画を見直している間にも大津波を伴う巨大地震が襲ってこないとも限りません。
この震災を教訓に、今後何時起こるか分からない地震災害(特に津波)に対する市民一人ひとりの備えとして、まずは、身の安全確保を最優先にした避難までの行動手順を取り急ぎ次のとおりまとめましたので、ご活用いただければ幸いです。
ステップ1グラッときたら(地震発生)

机、テーブルの下などにもぐり、揺れが治まるまでその場でじっと身を守る。
屋外にいたときは、ブロック塀の倒壊、看板や割れたガラスの落下に注意する。
ステップ2地震がおさまったら

- 家族の安全を確認する。
- 火気を使用していた場合は、火を消す。
- 非常持出品の携帯(普段からすぐに持ち出せるところに用意しておく。)
(注意)『懐中電灯』、『携帯ラジオ』、『貴重品(通帳、印鑑)』、『飲用水・非常食料』、『常備薬』などを持ち運べる範囲でリュックサックなど、背負うことができる袋に入れておく。 - 火災発生の場合は、大声で周囲に知らせ、初期消火を行う。
- ラジオ、防災行政無線などで正しい情報を入手する。
ステップ3高台へ避難(津波のおそれあり)
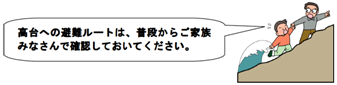
ラジオや防災行政無線などの情報から津波到達の可能性が予想される場合、直ちに近くの高台へ避難する。(必ず避難所へ行くものではありません。)
- ケガを避けるため、靴を履いて避難する。(時間があれば、電気のブレーカーを落とし、行き先を書いたメモを玄関など目立つところに残す。)
- 避難に車は使わない。⇒建物の倒壊や倒木により通路が塞がれ、通行できないおそれがある。
- 津波は何度も繰り返し来襲するので警報・注意報が解除されるまでは、海岸に近づかない。
- 海岸付近にいた場合は、直ちに高台へ避難する。
ステップ4避難所へ移動
津波などにより、帰宅が困難になった場合に、避難所へ移動する。
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 防災危機対策室
電話番号:046-882-1111(内線60640・60641・60642・60643・60644)
ファックス番号:046-864-1166
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-











更新日:2025年12月19日